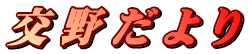ホーチミン市内の夜景
ミトーからバスで2時間かけホーチミンのホテルに22時頃到着です、ホテルから見るホーチミンはく光の乏しい夜景です。 |
|
|
|
|
ホーチミン名物バイクの洪水
ベトナムの人口は9000万人、ホーチミン人口900万人でバイク台数はなんと600万台です。通勤時間はまさにバイクの洪水です。 |
|
|
女性のバイクファッション
女性は日焼け対策でカラフルなマスクをします、そうすると年齢がわからなくなります。ベトナム男性は積極的で、
バイクの女性を口説き、相手にしてくれるまで追いかけていきます。女性が漸く止まってくれマスクを外すとなんだ
おばさんかと立ち去ることが間々あるそうです。
ミニスカートの女性は腰に風呂敷?を巻き足を隠します。うら若き女性が路上で風呂敷を巻いていましたが、なんとなく
どきどきしてしまいました。
女性を口説くにはかっこよいバイクが必須で、高級車を持っていてもバイクを購入するそうです。 |
|
|
団塊の世代にはベトナム戦争の記憶が間生なしくあります。ベトナム戦争は4月30日にこの大統領府に北ベトナム軍が突入しベトナム戦争は終わりを告げました。
南ベトナム最後の大統領「ズオン・バン・ミン」は
4月28日に大統領に就任しわずか2日間の大統領でした
|
 |
|
 |
北ベトナム軍の戦車が8時30分にこの門を押し破り進入した映像は大変有名です。
1台目は副門を押し破ったところで動けなくなり、2代目が正門に突入し一番乗りを果たしました。
戦車は2012年に2台ともベトナムの国宝に指定され博物館で大切に保管されています。
門はフランス統治時代の影響かベルサイユ宮殿の門に似ているような気がします。 |
2階テラスからの景色
北ベトナム軍が大統領官邸に突入したときはこの通りを北ベトナム軍が埋め尽くし、戦車が門を突き破るのをこのテラスカラ見ていたと思います。 |
|
|
|
|
突入した戦車と同じ型の戦車
最初に副門に突入し動けなくなったソ連製T54B戦車 本物の843号はベトナム軍事博物館に展示されてます。
大統領官邸の屋上に旗を立てたのは、843号の車長です。 |
|
|
突入した戦車と同じ型の戦車
中国製T59戦車 390号
先頭を切って突入した843号が動けなくなったため、後から来た390号が正門を突破して一番乗りとなった。本物の390号は戦車・装甲車博物館に展示されている。
写真左はベトナム人ガイドの説明を聞いてるアメリカ人観光客。 |
|
|
見学の学生
ベトナム統一の歴史を学ぶ取り組みがされているようで、ベトナム戦争の史跡には学生や若者が見られます。 |
|
|
|
大統領官邸のヘリポート
赤ペンキで丸と文字を書かれているのが、爆弾が投下された跡です。第3代大統領グエン・バン・チューはサイゴン陥落
直前の4月21日大統領を辞任しこのヘリポートから台湾に亡命した。 |
|
|
| 大統領応接室 |
 |
副大統領応接室 |
|
|
|
台湾から贈られた龍と鳳凰のカーペット。龍と鳳凰は「権力の象徴」を意味しています |
|
|
| 南ベトナム大統領、国内賓客応接室 |
 |
国書提出室 |
|
|
|
| 中庭を中心に大統領寝室・家族の食堂・大統領夫人の寝室があります。 |
 |
|
|

|
ドンコイ通り
| ドンコイ通りはサイゴンのシャンゼリゼも言われています。コロニアル様式の建築を見ていますとそうかなと納得です。 |
|
|
ベンタイン市場
伝統様式により建設された巨大な堂の中に個人商店が数畳の店を構えてひしめき合っている屋内市場です。果物・魚・食料品・日用品・土産物・花・食堂やカフェ、なんでもそろっておあり地元の人や観光客でごった返しています。日本人にはふっかけるそうですので、楽しみにしていましたが、まったく買う気がないのがわかるのか、声をかけてもらえませんでした。同じツアーの人はスカーフを値切りに値切って購入されました。しかしふっかけられているかも?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サイゴン大教会
フランス植民地時代に1863年から1880年に建設されたネオ・ゴシック様式の教会です。カトリック教徒も多いベトナムにおいては、多くの敬虔なホーチミン市民がミサに来るそうです。当日もちょうどミサの最中で内部には入れませんでした。
|
|
|

中央郵便局
サイゴン大教会の道を隔てて隣にある中央郵便局の設計者は、あのエッフェル塔を設計したギュスターヴ・エッフェルです。同じくパリにある(当時は駅舎だった)オルセー美術館をモデルにしており、コロニアル建築様式の粋が集められています。内部のドームは駅のホームの名残が感じられオルセー美術館の雰囲気を感じます。しかし駅ではなく元から郵便局で、現在も業務を行っています。
|
|
|
夕食後 飛行機にて次の目的地フエに向かうため空港へ
|
飛行機からホーチミン市の夜景 |
| 飛び立ってすぐは明かりがありますが、1分ぐらいの間に漆黒の闇に変わっていきます。 |
|
|
 |
|
|
        
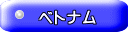 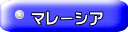 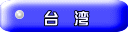 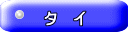 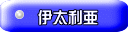 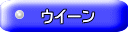
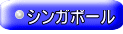 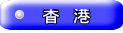 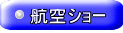
Copyright ©katano Dayori All Rights Reserved
|