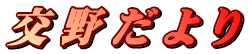|
祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことはりをあらはす。
おごれる人も久しからず、只(タダ)春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。
平家物語の有名な一節で沙羅双樹は広く知られています。この中で詠われている「沙羅双樹」は仏陀が満80歳でクシナガールの地で涅槃に向かったときに、2本の「沙羅の木」の間に横たわり、涅槃に向かうその時、沙羅の木の薄い黄色の花が白く変わったと伝わっています。このことから2本の沙羅の木「沙羅双樹」と言われ、仏教では「無憂樹」「印度菩提樹」と並んで三大聖木とされています。
写真上左・写真下右は東南アジアの「沙羅の木」です。
日本における「沙羅双樹」はツバキ落葉樹の「ナツツバキ」(写真下左」のことです。初夏に白い花をつけます。この花の寿命はわずか一日で、朝に咲き、夜には落ちてしまいます。このはかなさが「盛者必衰」を表していると考えたのではないでしょうか。
印度における「沙羅の木」(写真下中)はインド原産のフタバガキ科の常緑樹で高さは30mになります。
|